copy right 1998,05
![]() はじめに
はじめに
ボールスプライン事件の最高裁判決は、均等論適用の要件を最高裁判所が積極的に表明した恐らく初めてのケースとして、各方面から注目されている。しかし、この判決は、むしろ均等論の限界,別言すれば権利範囲拡張の限界を示したものと考えるべきであろう。検討結果を報告する。
![]() 最高裁判決の内容は?
最高裁判決の内容は?
詳細は省きますが、
『イ号製品は、公知技術を組み合わせたものにすぎない。この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、イ号製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえない。』ということです。
これをあえてイメージ化すると、次のようになると思われます。
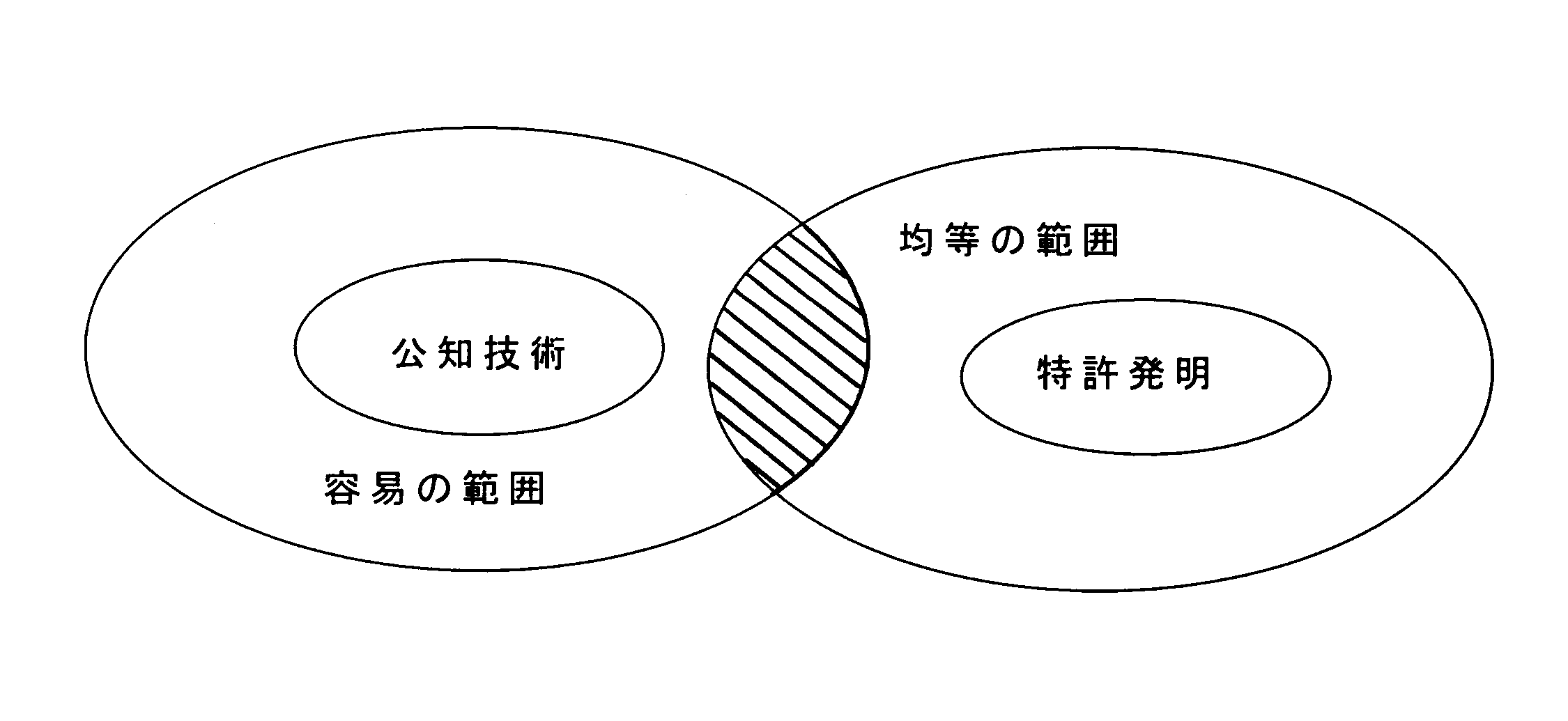
公知技術から容易に考えられるものは、特許法29条2項の規定により特許を受けることはできません。従って、出願発明が特許されるためには、容易の範囲の外側になければなりません。一方、均等論は、特許発明と同一の範囲を超えて実質的同一の範囲までを権利範囲として認めようとするものです。
ところが、容易の範囲と均等の範囲が、図示のように重なることもあると思われます。この重なり部分をどのように考えるかということですが、(1)均等の方を優先して権利侵害とする,(2)容易の方を優先して非侵害とする,のいずれかということになります。今回の最高裁判決は、後者の立場であることを示したものといえます。特許権を主張する以上、特許要件を満たしたものでなければならないということです。
このような考え方は、特許のみならず意匠にも適用され得ると考えられます。意匠の場合、独占排他権は、同一のみならず類似の範囲にまで及びます。従って、次の図に示すように、公知意匠に類似する意匠が登録意匠の類似範囲に含まれるというような場合が生ずる可能性があります。
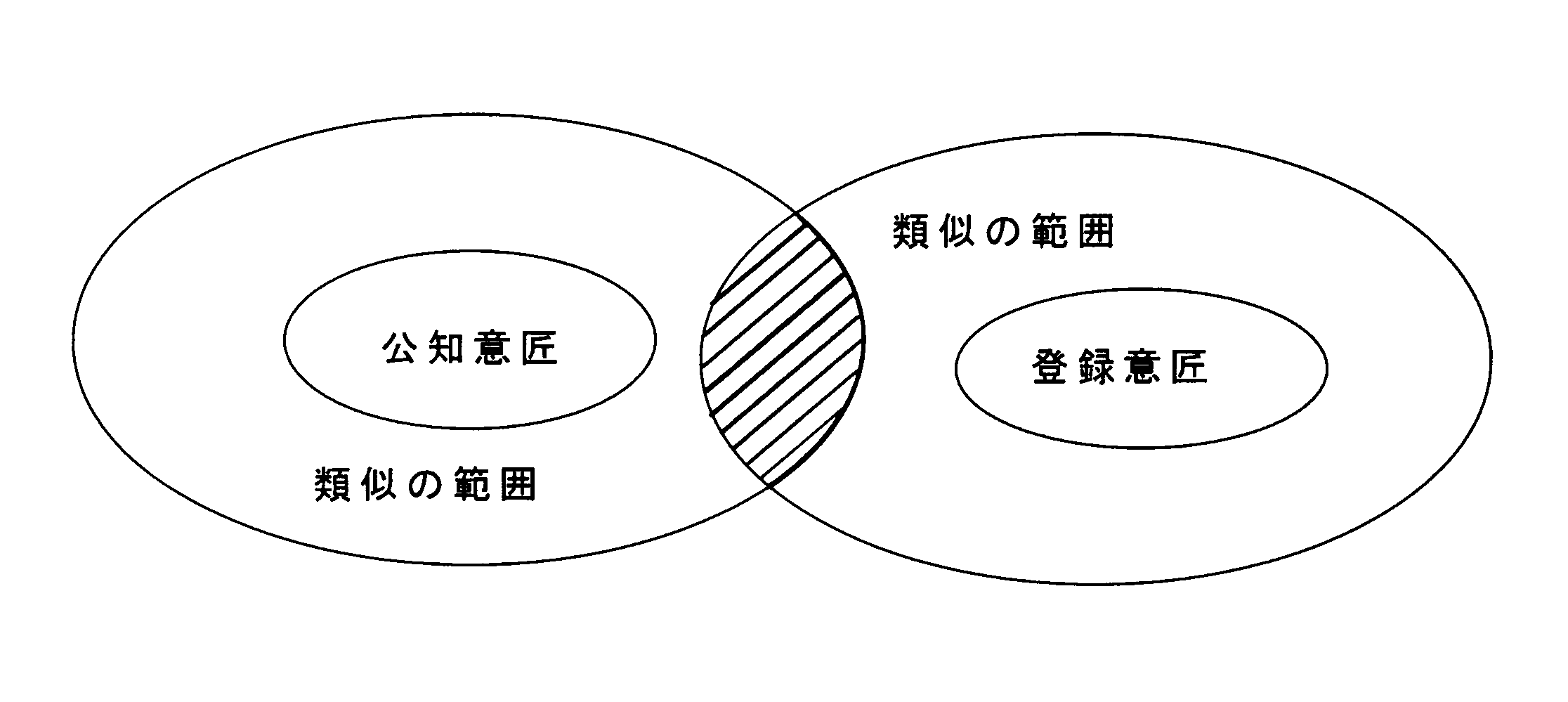
この場合、類似範囲まで意匠権の効力を認めているのであるから、公知意匠に類似する意匠の実施が制限されてもやむをえないという考えが支配的のように思えます。
しかし、公知意匠に類似する意匠は、意匠法3条1項の規定により本来的に意匠登録を受けられないわけですから、そういう意匠に独占権を認めることには、本件判決の趣旨からして妥当でないように思われます。
なお、意匠権における類似範囲については、諸説入り乱れた状況が続いていますが、審査を行って意匠権を付与するという審査主義の建前からすれば、意匠権の範囲は審査官が審査した意匠(あるいはれと同一とみなされる範囲まで)であると解するべきであろうと思います。
すなわち、意匠権の効力が及ぶ範囲である類似範囲も含めて審査された範囲であり、審査を経た意匠の権利範囲の周囲に審査を経ていない類似という権利範囲が付与されるとすべきではありません。類似範囲が審査範囲外であるとすると、審査されていないものに独占権が付与されることになり、審査主義の建前に反する結果となるからです。
してみると、意匠権の効力が及ぶ範囲は、六面図に表された意匠と同一の範囲及びそれと実質同一の範囲ということになります。しかし、これではあまりに権利範囲が狭くなり、意匠制度の存在意義が問われるようなことになってしまいます。
これは、現行制度が六面図に表されたデザインそのものを審査対象,ひいては保護対象とするところに原因があると思われます。ストライプ模様をつけるとか、流線型にするとかいうようなデザインコンセプト,特許流にいえばデザイン思想を保護対象としなければ、十分な保護を図ることはできないと思います。
次に、商標の場合を検討します。例えば、下図のように、普通名称の類似範囲と登録商標の類似範囲が重なったとき、その重なり部分の商標使用はできるのでしょうか。
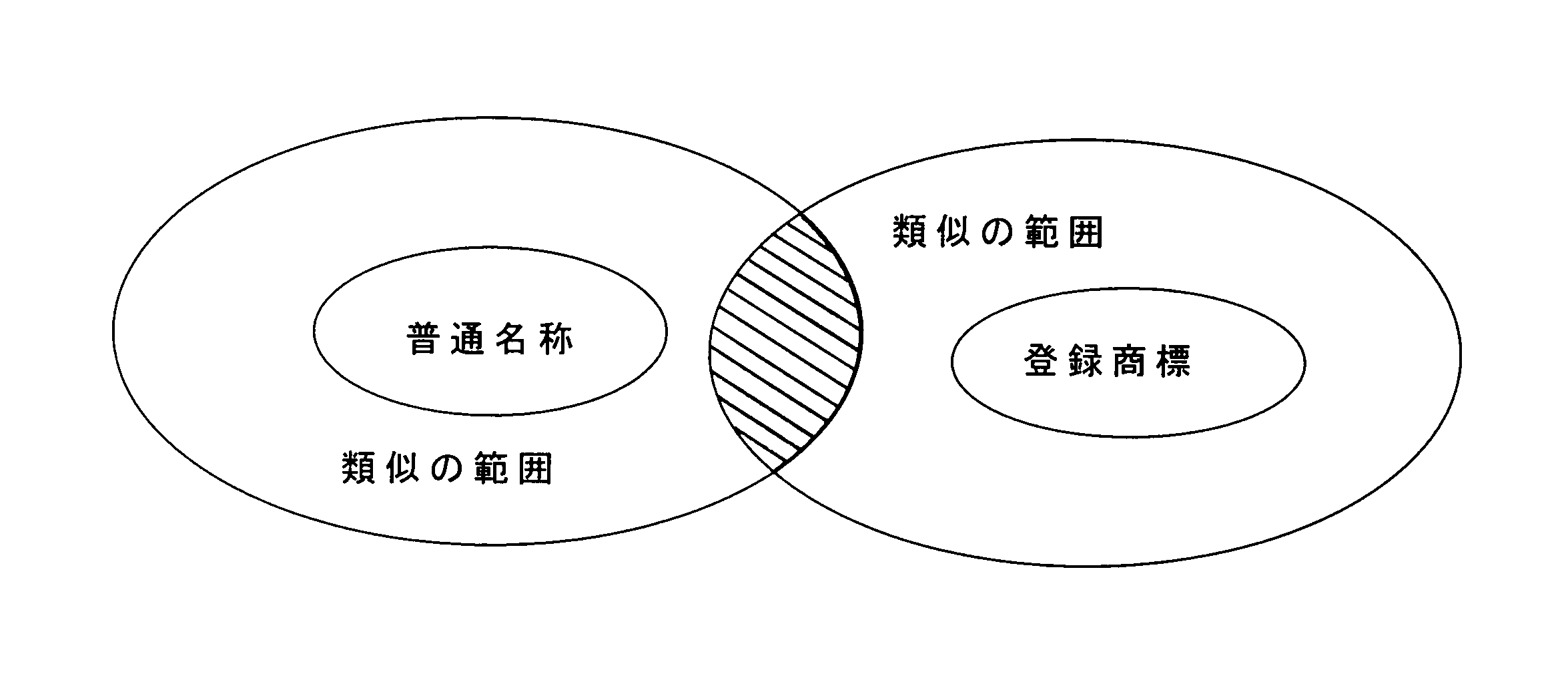
商標権における類似範囲は、出所の混同が生じないようにするための緩衝地帯であり、商標権者といえども事実上の使用ができるにすぎず、意匠権における類似範囲のように独占権があるわけではありません。商標の場合には、流通秩序の維持という観点からすれば、重なり部分については緩衝地帯として商標権の禁止的効力が作用すると考えたほうがよいように思われます。
![]() 均等の要件は?
均等の要件は?
本判決では、均等が認められるための要件を、
(1)特許発明の本質的部分ではなく、
(2)対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
(3)置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(4)対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5)対象製品等が出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき、と示しました。
これで均等の要件が明らかになったのだから、今後均等論がどんどん適用されるだろうと考える向きもあるようですが、むしろこれらの条件を満たさないと均等論は認めてもらえないと考えるのが妥当なように思います。
それは、判決文中で『対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70条1項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、…(以下、均等の条件)』と述べていることから明らかなように、最高裁は均等論を原則に対する例外として解しています。例外であり、しかも明文の規定はないわけですから(法制化の動きがあったが産業界の反対で実現せず)、その適用は慎重に行われると考えたほうがよいようです。出願時点から均等論を当てにしているようでは、先が思いやられると言えましょう。
![]() 均等判断の時期的基準は?
均等判断の時期的基準は?
イ号が均等物に該当するかどうかの判断を出願時で行うという立場と、侵害時で行うという立場がありましたが、本件判決では、
『特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる』とし、侵害時を基準とすることを明らかにしています。
ただし、侵害時で判断するのだから、出願時における均等物は当然権利範囲に含まれるということになるかというと、どうもそれは微妙なようです。出願時点で置換可能,置換容易なものをクレーム中に含めなかった場合は、意識的に除外したのではないかと認められる可能性もあると思われます。